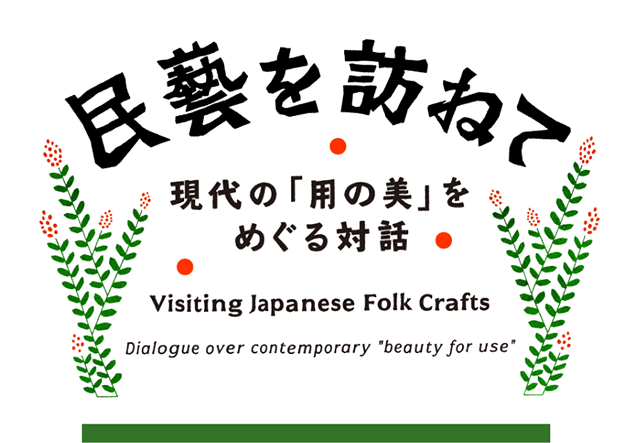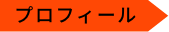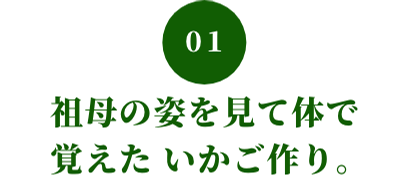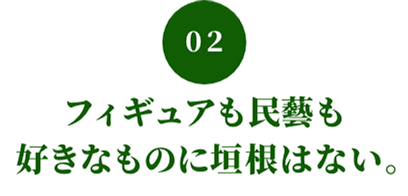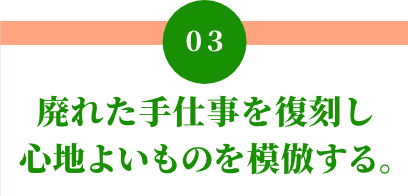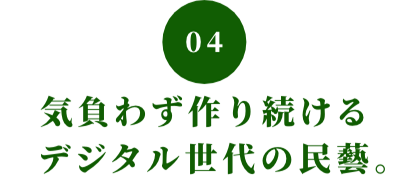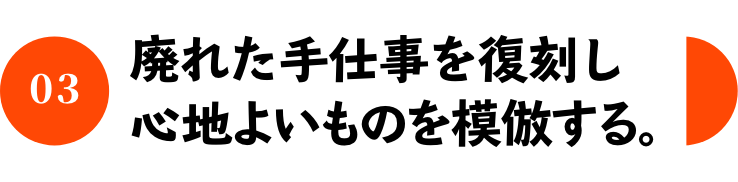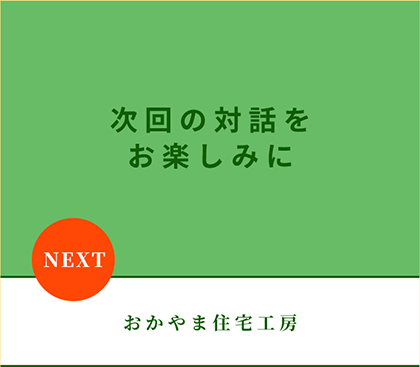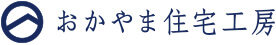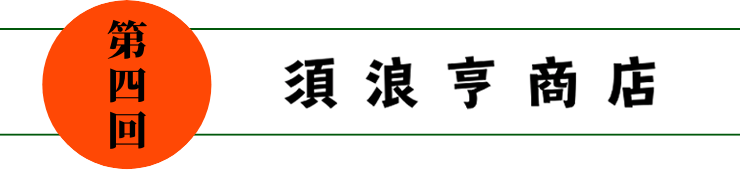

おかやま住宅工房
中川 大
NAKAGAWA Futoshi

中川
私がこのいかごを手に入れた時は「いかご」という言葉を知らなかったんですよ。問屋町にある『くらしのギャラリー』はたびたび覗いていて、店の方が勧めてくれたんです。僕はいつもこの籠と同じサイズのカバンを持ち歩いているんですけど、店の方に「これ、どうやって使うんですか?」と聞いたら、「Mac 入れてね、仕事で東京に行きます。意外と目立つんです。」と言われて。その後、持ち手を修理してもらった時に、瓶を入れる細長い籠をつけてもらいました。
でも、この籠を作る方が、先入観で想像していたイメージの方と全然違っていて、まさか20代の方とは思わなかったです。しっかりいろいろな民藝のものを集めていらっしゃるのにもびっくりしました。この雰囲気はうれしいですね。こういうコレクションもしつつ、インスタグラムにも載せたりというのが、僕たちからしたら今の若い方の感覚ならではだなと思いますね。民藝で興味をもった作品があったら、それを実際に買ったり、本を読んだり、人に聞いたりして勉強しているんですか?
でも、この籠を作る方が、先入観で想像していたイメージの方と全然違っていて、まさか20代の方とは思わなかったです。しっかりいろいろな民藝のものを集めていらっしゃるのにもびっくりしました。この雰囲気はうれしいですね。こういうコレクションもしつつ、インスタグラムにも載せたりというのが、僕たちからしたら今の若い方の感覚ならではだなと思いますね。民藝で興味をもった作品があったら、それを実際に買ったり、本を読んだり、人に聞いたりして勉強しているんですか?
須浪
そうですね。勉強しているというほどでもないんですが、作家さんの個展や展示会、骨董屋で作品を買うことが多いですね。
中川
このカテゴリーは理解できない、というのはないですか?僕などは、布のことが良くわからなくて、この民藝の取材で倉敷本染手織研究所へ伺って初めて面白さが分かったんです。
須浪
僕はそれでいうと、完全に関心がないのは食べ物ですね。食べ物と音楽は関心がないんですよ。もうちょっと食生活に気をつけなさいと言われるんですけど。よく食べるけど、何でもいいんです。でも自分の身体で実験するのは好きで、お肉はもう数か月食べてないですね。工房の近くをランニングするんですけど、お肉を食べていない日の翌日は明らかにタイムがいいんですよ。

中川
籠を作るのに、何か新しいことをやってみようと思うことはあるんですか?
須浪
ありますね。僕が作っているものは大きく分けて2種類で、一つは昔の仕事の復刻です。イ草でやっていた仕事というのがあって、今残っている仕事より、なくなった仕事の方が多いです。そういうのを調べたり、骨董市で買ってきたものを見て復刻することです。このあいだ珍しく自分の展示会をして、そこに出品したんですけど、織り機で織るようになる前の闇籠とかは、木の箱を型として使って、手で編んでいくんです。

もう一つは、ほかの産地から集めたもののサイズ感とか、「これいいな」と思うサイズ感の籠の形や編み方を模倣してみることです。もともと僕は作家志望ではないので、こういうものが作りたいというのはあまりないんですよ。
「復刻」と「模倣」があって、それを組み合わせることもあります。もともとこういう作り方があるけど、このサイズ感でやってみようとか、この仕様を取り混ぜてやってみようとか。自分でひらめく時もあるけど、それも今まで見てきたものを自分の中で咀嚼して、たまたま出てきたんだろうと思います。そこにある大きい籠は、IKEA のショッピングバッグのサイズ感を真似してみました。形は同じでも素材が違うと違って見えるんです。
「復刻」と「模倣」があって、それを組み合わせることもあります。もともとこういう作り方があるけど、このサイズ感でやってみようとか、この仕様を取り混ぜてやってみようとか。自分でひらめく時もあるけど、それも今まで見てきたものを自分の中で咀嚼して、たまたま出てきたんだろうと思います。そこにある大きい籠は、IKEA のショッピングバッグのサイズ感を真似してみました。形は同じでも素材が違うと違って見えるんです。
中川
作り方は変えずに、使い勝手を今の生活感にアップデートするという感じですかね。作り方とかを見るために、買ってきたものを一度ばらすこともあるんですか?
須浪
ありますね。2個ぐらいあるとばらすんですが、1個だと踏ん切りがつきませんけど(笑)。

中川
おばあさんの様子を見て作れるようになって、今はこれを生業にされて、おばあさんもびっくりされているんじゃないですか?
須浪
びっくりしてますね。この先どうなるかはわからないですけど。もの自体を見ればある程度作り方はわかるんですが、こうやったら作りやすいとか、無理がないとか、手の動かし方まではわからないので、そういうのは実際に作り方を見てみないといけないです。ある程度、数を作っていると、定番の籠でも、より作りやすい工程に修正したりするんです。僕の場合、その気づきは、やってみないとわからないタイプですね。
新しいものを作ろうとして絵を描いて作ってみるんですけど、結局絵を描いたことに意味があったのか分からなくなる。経験の浅さからか、想像できない部分もあって、作っている途中に全然違うものができて、そこから修正していくタイプですね。
新しいものを作ろうとして絵を描いて作ってみるんですけど、結局絵を描いたことに意味があったのか分からなくなる。経験の浅さからか、想像できない部分もあって、作っている途中に全然違うものができて、そこから修正していくタイプですね。
中川
手を動かしながらアイデアが浮かんでくるんですね。個展は定期的にやろうとか、思われているんですか?ほかの作り手の方からコラボを持ちかけられるかもしれませんね。
須浪
前回の個展がほとんど初めてで、何年か後にまた機会があるかもしれないし。コラボの願望があるかといえば、そうでもなくて。個展の締め切りがあってそこでいろいろやっていいという時間があるのはいいことなんですけど、何かを作って社会に訴えかけたいという衝動はあまりないんですよ。
中川
「大きなことをするのではなく。」というのは、暮らしに一番近い「民藝」という立ち位置ですよね。

須浪
民藝運動的なことはしたいんですけど、それが民藝のものではなくても、自分が選んで、それが好きで使っていれば、それでいいんじゃないかと思うんです。ただ僕は籠やこうして集めているものが好きなので、人に勧めたりもしますけど、どうするかはその人が選ぶことだと思いますね。柳さんとか外村さんを見ていると、僕はそこまで強い思いはないというか、誰かの思想に傾倒できるような人間ではないので。
中川
結構、須浪さんも思想的な面があると思いますよ。
須浪
僕は本とかを読んでもフラットな気持ちになって、思想に打たれるとかがないんですよ。ただ、僕のような仕事や民藝と関係ない友達から見ると、僕もわりと思想強めかもしれませんね。
【つづきます】
くらしのギャラリー
民藝の手仕事を紹介、販売するギャラリー。岡山県における民藝運動の拠点として創設された岡山県民芸振興株式会社が運営している。
民藝運動
「民衆的工藝」を「民藝」と呼び、日本各地に残る機能的な美しさを備えた日々の暮らしの道具を保存し、普及、発展させていった運動。大正時代末期以降、提唱者である思想家・柳宗悦(やなぎ むねよし)らが日本各地を訪ね、手仕事を発掘していった。